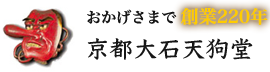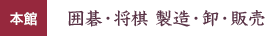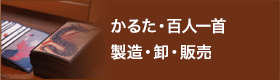将棋の豆知識47〜48 光風社 将棋101話 転用
47 浪花狂歌-2011.9.01-
近世の狂歌には、二つの流れがある。一つは、中世末期に京都の貴族のあいだに興り、しだいに庶民の手にわたって、大阪を中心に流行した。「浪花狂歌」とも呼ぶ。
いま一つは、近世中期に入って武士のあいだに興り、江戸の庶民がもて遊び、やがて全国的にひろがって行った。天明年間、にわかに盛んになったところから、「天明狂歌」の称がある。
狂歌は、古典和歌の優雅のなかに滑稽を織りこむところに独得の技巧がある。原歌の一部をすりかえる面白さ。原歌を卑俗の泥水にひたして眺める滑稽さ。原歌は、小倉百人一首が一番多く用いられている。
浪花狂歌の作者としては、古くは、雄長老や安楽庵策伝の名が知られている。
策伝和尚の『醒睡笑』のなかに、将棋を扱った。笑話があり、狂歌を添えている。
巻一の「落書」の部第3話に、信長の馬揃えのことを綴って、
金銀をつかひ捨てたる馬揃へ
将棊に似たる王の見物
ときは天正九年(一五八一)二月二十八日。『信長公記』によれば、その日、信長は高砂大夫の出立で、梅の花を折って首に挿していたという。五百石の身で名馬を曳いて信長を驚かせ、出世の端緒をつかんだ山内一豊の逸話は、その馬揃え—観兵式の日の出来事である。
巻四の「そでない合点」の部第28話に、「囲碁の入り王」と早合点の話を書いて、
王ゆゑに歩をも馬をもたて置て
かくきやうの外に使ふ金銀
狂歌は、建仁寺に佳した五山の代表的学僧の一人である雄長老の作。将棋の駒尽しという洒落たもので、王、歩、桂馬、角、香車、金、銀を詠みこんである。「歩」には人夫、「馬」には乗馬の意を掛けてある。
近世に入って、松永貞徳、石田未得、半井卜養などは、上方、あるいは江戸にあって、狂歌作者として名が高かった。
石田未得の『吾吟我集』、巻第一に「春駒」と題して、
いさみぬる将棊のごとし春駒は
とらんとするに手もささえざる
巻第九に「老たる人のわづらひ、よくなりての又のとしに」と題して、
春よりも行歩自由になりたりし
ハルは将棊のことまがへり
油煙斎貞柳(永田貞柳)も、浪花狂歌の代表者である。将棋の句が三つある。
世の中よ何と将棊のこまりもの
はるもよしなや捨てつまらす
金銀はあるも猶よしなしとても
人間万事宗桂がこま
将棊にて暮らすはあたらひまの駒
つまり果たる老の命を
江戸の著名な漢学者、松崎慊堂の「慊堂日暦」に、貞柳は大阪の墨工で、「月ならで雲の上まですみ登る/此はいかなるゆえんなるらん」と詠んで、「油烟斎の号を賜る」と号の由来を書いてある。
48 天明狂歌-2011.10.01-
「天明狂歌」は、初めは武士のあいだで興った。一方の旗頭である唐衣橘洲は、小島謙之、田安家の臣である。別号は酔竹庵。古典的な着想と巧緻な技巧で一流をきわめた。
天明五年(一七八五)正月、須原屋伊八開板の『徳和歌後万載集』巻八に、「囲者恋」と題して、
いかんせん象戯の駒とすてられて
囲はるる身の末も詰らず
「囲者恋」は妾。その妾のはかない運命を「囲う」「詰る」という将棋の縁語にかけて、老朽の作である。同書は、当代の作者二百六十余名の作品を集めるが、将棋を詠んだのは、この橘洲の一句だけ。囲碁を詠んだのは二句。狂歌は、川柳よりは将棋を題材とすることが困難であったせいであろうか。
妾のことは「囲者」と書く。同じ妾でも、「被囲」と書けば、川柳では僧の外妾のことをさすのが通例であったという。
オーソドックスな橘洲とは作風を異にする「天明狂歌」の代表者、四方赤良は、放胆な滑稽、鋭い機知で狂歌に新風を吹き入れた。四方赤良(南畝・蜀山人)こそ、「天明狂歌」を完成した人というべきであろう。
天明七年に出た『万載狂歌集』(四方赤良選)には、
金銀のなくてつまらぬ年の暮
何と将棋のあたまかく飛車
将棋と年末のやりくりという二つの主題を対照させて、蜀山人独得の滑稽を打出している。いや、決して豊かではなかった下級武士、蜀山人の苦しい体験を詠んだものであろうか。天明期の代表作の一つである。
天神の茶屋の前なるかけせうぎ
飛車とつぶれてかく成りにける
「天神」は、藤の名所で知られる亀戸天神。「かけせうぎ」は、掛け床几と賭将棋掛けている。巧みに将棋用語や駒の名を詠みこむところを見れば、蜀山人は、なかなかの将棋愛好家であったらしい。
同じく『万載狂歌集』には、「寄中将棋祝」と題して、
聖代になりゆく駒や中将棋
いきほひもよき麒麟鳳凰
一丈帯武の作。「麒麟」「鳳凰」は、中将棋にある駒で、古将棋の一つである中将棋が、そのころに江戸で試みられていたことがうかがえる。狂歌としては凡作である。
つはものの金こしらへの太刀先に
おいしやも銀の匙をなげけり
作者は、水行形。これも凡作である。
天明期は、四方赤良のほか、手柄岡持(朋誠堂喜三ニ)、尻焼猿人(姫路藩主酒井雅楽頭忠以の弟の忠因、画名は抱一)、朱楽管江(幕臣の山崎景貫)、万象亭(幕府の医官、桂川甫周の弟、森島中良)など、狂歌歌作者には武家が多い。
やがて、町人の作者もつぎつぎと名乗りを挙げ、狂歌の場を通じて武士と町人との新しい交歓が始った。
「天明狂歌」の存在価値の一つは、そうした新しい文芸の場が生れたことでもあったように思う。