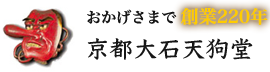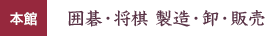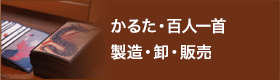将棋の豆知識87〜88 光風社 将棋101話 転用
87大阪の将棋指し -2015.05.01-
大阪には風変わりな棋士がいた。銭の計算が下手くそで、天下に名を轟かせながら、死ぬときは無一文。そんな人もいる。
飲む・打つ・買う。平気でそれもやる。つかみ合いもするし、喧嘩別れもする。それでいて、一本、しゃんと筋が通っている。貧乏なんぞは、くそくらえ。万事にあけすけで、どこまでいっても憎めない。
明治の世に生まれ、大正から昭和初期に生きた人には、そういう愉快な棋士がいた。
坂田三吉も、その一人であった。坂田と対立関係にある東京の関根金次郎門の木見金次郎(贈九段)もそうであった。
無類の善人で、酒が好きで、女遊びが好きであった。中年からプロに転じ、将棋だけでは食えず、饂飩屋を開き、それでも門下生を養っていた。
そのころ東京からきて入門した大野源一九段は、饂飩の出前もした。「先方に着いて、饂飩がのびていてはあかん。饂飩粉の練り方も、天気具合で水の加減をしたもんですわ」と述懐する。師匠は、ダシの作り方でも、美食家であったから、ことのほかうるさかったらしい。
饂飩屋は繁昌したのに、貸倒れが多くてつぶれてしまった。気の弱い木見は、貸金の取立に行っても、相手の顔を見れば切出せず、逆に小料理に誘って御馳走してしまう。
貧乏しても、将棋が指せれば満足した。門下に、大野をはじめとして、升田幸三九段、大山康晴名人と戦後棋界の歴史を創った名棋士が輩出した。弟子には何もいわず、将棋だけは一所懸命に指せといった。勝って帰っても、持時間を余していると、「こんなこっちゃ、出世できん」と、そのときばかりは小言をいいつづけた。
戦災に会ってからは各地を転々としたが、将棋が指したくてたまらず、ついに大阪の弟子の家に戻ってきた。朝早く起きて原稿を書き、あとは将棋と酒で日を送った。弟子宅で74歳の生涯を終えたのは、昭和26年1月7日の午前9時30分。朝から好きな酒を呑み、酔い痴れるごとく息絶えたという。
木見家の食客の一人であった神田辰之助(贈九段)も、最後の大阪の将棋指しらしい勝負師であった。
反逆児といおうか、いや、それ以上に熱血漢であった。八百屋の車ひき。浪曲師の前座を勤めてドサ廻り。郵便配達夫。いろんな職業を渡り歩いて、結局は、一番好きな将棋の道に自分を賭けた。
勝負にかけては、情は無用とした。弟子と将棋を指しても、金を賭けて巻き上げた。宿敵の木村義雄に勝ち、「好局を失って・・・」と木村がいうと、「何で勝っても勝ちは勝ち」とぴしゃりとやっつけた。
その木村と昭和17年に名人位を賭けて争って、四連敗を喫した。そのとき、すでに胸をおかされ、常人では対局に耐えない躰であった。負けても、頑張り抜いた。
ある初夏の夕暮、心斎橋で神田は仲間の夫人と出くわした。二十貫の巨体が、枯木のように痩せ細っている。夫人は慰め顔に、「血色もようなって・・・」というと、
「なに、いいまんね」
と神田は、ドスの利いた声で、「—今年いっぱい、もちまへん。嘘や思うなら、賭しまひょ。わては、わてが死ぬほうに賭けまっせ」
その言の通り、ほどなく神田は52歳を一期に世を去った。
88巨星墜つる日に -2015.06.01-
王者交替二十周期説を私は考えている。先輩を倒し、同輩を退け、追いすがる後輩を蹴散らして、初めて、王者の地位は安定する。
大正期から昭和初期まで二十年、その間第一人者の名をほしいままにした土居市太郎は、木村義雄の抬頭で王城を明け渡した。その木村は、先輩・同輩・後輩を撫で斬りにして、天下取りは二十年の長きに及んでいる。
「常勝将軍」とも「将棋の神様」とも、世間の人は呼びつづけ、あるいは「不世出の名人」とも語り継がれてきた。とにかく強かった。
木村に衰えが見え始めたのは、王将戦で升田幸三に敗れ、名人戦の檜舞台で大山康晴を挑戦者に迎えたときである。こんどは木村危し、という声が強かった。その木村の最期を見んものと、大阪府高石市の羽衣荘へ名人戦第五局の観戦に赴いた。
その瞬間を、この目で私は見た。
・・・昭和二十七年七月十五日午後十一時五十二分。残り一分の声に、木村はがくっと肩を落して、「これまで・・・」と呟いた。大山は黙って頭を下げた。
新聞記者はすぐに新名人を取囲んで、一せいに質問の矢を浴びせかけた。若い大山は、うつむいて言葉を発しない。すると、ぽつんと取残されていた木村は、突然、
「では、私が代って—」
と新名人の温厚な人柄を讃え、よき後継者を得て嬉しいと語りはじめた。
話半ばで席を立って、私は廊下に出た。ほの暗い廊下の片隅には、木村と親しい渡辺東一(名誉九段)と、丸田祐三(九段)が藤椅子に身を埋めていた。二人とも、唇を噛みしめて、あらぬ方角に視線を泳がせていた。
はずんだ木村の声は、そこまでも聞えてきた。
それから何時間か経って、私は木村の部屋を訪れた。明け方に近かった。浴衣に着替えた木村は畳の上に足を投出し、両手で上体を支えて、じっと天井の一隅をみつめていた。
めっきり白さを増した頭髪。蒼ざめてこわ張った横顔。数時間前、衆人環視のなかで華やかに千両役者振りを披露したその人とは、まるで別人である。その傍で、年来のファンである稲垣九十九が、泣きはらした目で木村を見守っていた。
木村は、闖入者のほうを一度だけ見た。眼鏡の奥で、その目は、あてもなくさまようかのごとくであった。—私は、かみしもを脱いだ孤独な勝負師の魂を初めて見る思いがして、黙って外に出た。
翌日の新聞は、木村の敗戦を「巨星堕つ」と報じていた。王座を明け渡す瞬間、木村の沈着を讃える記事もある。その記事を読みながら、明け方、哀しみをこらえていたその人の素顔を知る私は、いいようのない複雑な気持であった・・・。
あれから二十数年の歳月がすぎ去った。いまも、あの明け方の木村の表情は瞼から消えない。あのころは私も若かった。若かったから、勝負師のぎりぎりの気持を追い詰める勇気があった。いまなら、多少は訳知も知る年となって、夜明け、敗者の悲しみの部屋に飛びこむことができるであろうか。
敗れて、四十八歳で木村は現役を去り、永い大山時代が始った。二十余年すぎ、その大山にも転機が訪れて、新しい歴史が始まろうとする。
どうやら、勝負する者にとって、それは避け難い宿命であるらしい。