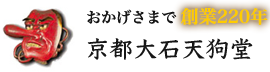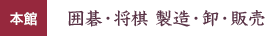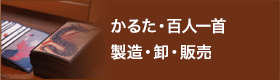将棋の豆知識93〜94 光風社 将棋101話 転用
93調理問答 -2015.11.01-
過日、将棋会の席で観戦記者某氏は、自らを調理人になぞらえた。以下、某氏が語った言葉を再録する。
観戦記者は、新聞の読者の代理人である。ライターというよりは、調理人といったほうが適切であるかも知れない。棋譜という素材を煮たり、味つけしたりして、読者の食膳に供する任務を背負っている。
ただ、本来の調理人と異るのは、材料の選択権がないことであろう。与えられた材料をいささかも味を損なわずに調理する。それが絶対的な条件となっている。
人は、観戦記は易しい仕事だという。すでに材料が与えられ、それを調理すればよいという。ある人は、素材は「与えられたもの」であって、さほどに腕を振う余地が残されていないという。
どちらも真実であり、どちらも遁辞であろうと私は思う。
ところで私は、最近、自分が書いた観戦気で二人の若い棋士から抗議を受けている。一人は、新鋭が大先輩に勝ち、それを大先輩の怪我負けらしく書いたためである。
抗議の主旨は、観戦記によれば、大先輩にポカがつづき、結果的に新鋭が勝った。その書き方が不満だ、とその棋士はいう。
もう一人は、「棋士が命をけずる思いをして創作した将棋を、下手な観戦記者の筆で汚されてしまう」と口惜しがった。これは、私の観戦記に対してだけではなく、観戦記一般についての不満であるらしかった。
後者の抗議は、まことに、ごもっともで、黙って頭を下げるしかない。
碁の世界では、もっと意地悪な抗議が出るらしい。私の友人は、対局中に着物の袖をまくったと書き、「僕は、そんなに無作法な男じゃないよ」と噛みつかれて、ほとほと困り果てている。
碁の人にくらべて、将棋の棋士の抗議は、ずっと純粋である。それにしても、不思議に思うのは、どうして名人やA級の人は抗議をしないで、段の低い人ばかりが文句をつけるのであろうか。
高段者は、観戦記者の限界を知っていて、目をつむってくれるのであろうか。しばしば、新聞に登場して、いちいち目くじら立てるのが煩わしいからであろうか。
むろん、私は、若手棋士の抗議を素直に受けいれている。決して不当とは思わない。抗議を受けるのは、何はともあれ、調理人の腕が未熟だからである。
これは、いつか、原田泰夫八段も嘆いていたが、九十九パーセントを褒めて、一パーセントをけなしても、棋士は、けなした一パーセントについて猛烈に喰ってかかるそうだ。だから、観戦記者は、その一パーセントの抗議を恐れて、ペンを曲げて甘く書く。まるで神様扱いにするという。
その点には異論がある。読者が、ほんとうに求めているのは、プロの修行を積んだ棋士の「人間臭さ」である。
それは、間違いないことだ。それに、調理人というものは常によい仕事をしたいと願っている。よい仕事をするために、「よい素材」の提供を願っている。・・・
冒頭で、観戦記者を調理人に見立てたのは、実のところ、そのことを訴えたかったのである。
94将棋奇人 -2015.12.01-
荷車ひきの新宮得平氏は、家の向いの長屋に住んでいた。何でも、若い時分、賭将棋で破産して夜逃げしたことがあるそうだが、口数の少い人であったから、真相はわからない。
彼は子福者であった。小柄な細君は、年がら年じゅう、大きなおなかをかかえていた。戦争末期には、七人の子どもを産んでいた。
最初に女が生まれて、けいと名づけた。二女はきん。一年おいて長男の京太郎が生まれ、つづいて三女のふき、二男の吟吾、三男の旺三が生まれ、四女のひさが誕生した。
何のことはない、生まれた子に将棋の駒の名をつけたのだ。将棋を知らない細君でも、けいは桂馬に通じ、京太郎は香車の駒銘からとったことぐらいはわかるが、文句をつけてもどなられるのが落ちだから、我慢した。しかし、得平氏とすれば、まだ不満である。七人では<角>の駒が足りない。細君はもう四十を過ぎていたが、彼はもうひとり男の子がほしい、とねだった。
ところが、このころ、思いがけないことが持ち上った。得平氏のライバルにウドン屋の小林幹太氏がいる。ある日、ふたりのあいだで、次のような会話がかわされた。
「得平サ、うちにがきが生れたら、角の字をもらうぜ」
「あかん。あかんぞ。角の字を盗んだら、たたきのめすぞ!」
得平氏は口をとんがらせて抗弁した。が、幹太氏は得平氏には無断で、生れたわが子に<角太郎>と命名した。
仕事から戻った得平氏は、血相を変えて飛び出したが、もうあとの祭り。その夜は大トラになって帰り、「角が足らん。幹太に角を盗まれたぞ!」とわめき散らした。
つぎの日から、得平氏はぷっつり将棋をやめた。縁台将棋を見ても、そ知らぬ顔で通りすぎる。むろん、幹太氏とは絶交だ。
戦後、得平氏は長屋を引き払った。七人の子どもが大きくなって、手ぜまになったから。同じころ、私は郷里をあとにした。
あれから、二十年。しかし、二十年たって、私は偶然得平氏の消息を聞くことを得た。数日前のことである。郷里で町会議員をする旧友が、陳情のために上京して拙宅に立ち寄った。懐旧談がすんで、私は、さっそく得平氏のことをきいた。
「得平氏サか、極楽往生や」
旧友は紀州弁丸出しで、「—なんせ、死ぬ晩まで、長男の京太郎サと将棋、やってたちゅう話やぜ・・・」
私は、なぜかほっとした。あの将棋狂の得平氏から将棋の楽しみを奪うのは酷だ。旧友は「角」の字にまつわるトラブルについては何も知らないふうであったが、もうそんなことはどうでもよい。
私は、昔の将棋家元は駒型墓碑を建立する習いであったことを説明して、得平氏も駒型の墓の下で眠るとよい、と言った。旧友は、けげんな顔をした。
別れぎわに、得平氏の七人の子どもはいずれも健在か、とたずねた。旧友はうなずき、指折り数えて、あわてて訂正した。
「七人やないぞ、八人やど。八人目は女の子で、ツミという名前や」
「おう、ツミ・・・」
私は手をうった。ツミは将棋の用語で「詰」だ。だぶん、幹太氏と和解して再び駒を手にした得平氏は、大長考のすえにこの妙手を発見してほくそえんだことだろう。
少年のころ、私は将棋に熱中したが、一度も得平氏と指したことがない。いま思うと残念でならない。