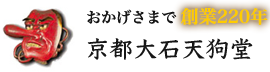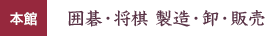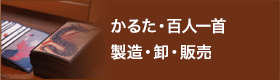将棋の豆知識89〜90 光風社 将棋101話 転用
89升田・大山時代 -2015.07.01-
昭和43年の暮、新聞につぎの文章を書いた。そのまま採録する。カッコ内に、記録と段位の更新を註記した。
戦後の将棋界は、升田幸三と大山康晴との抗争に明け暮れた。木見門の兄弟弟子は、「宿命のライバル」として、すでに大戦は151局(昭和51年6月1日現在は163局)。名人戦を含めて大山のタイトル獲得数は58回(優勝は109回・タイトル優勝は75回)、升田は7回となっている。
「高野山の決戦」以来、二人はどれほど数多く名勝負を演出したことだろう。戦後の将棋史は、まさに、この二人の手で書き替えられ、創られて行った。
「新手一生」と掲げる升田は、攻めて勝つことを将棋の理想とする。「勝負の鬼」と呼ばれることをきらい、自ら「将棋の鬼」と称してきた。「攻めるは責めるなり」と語る。身をきられるような攻め将棋の苦しさ。この一言に、升田将棋の本質がにじみ出る。
大山は、受け将棋である。戦後の棋界に、受けを主軸とする大山将棋が出現しなかったなら、将棋の技術は、これほど著しく進歩はしなかったろう。だれもが躍気となって、大山将棋の秘密をさぐり出そうとする。大山将棋は、いって見れば、将棋の宝庫であった。
「守りの駒は美しい」
長く第一人者の名をほしいままにし、受け将棋に徹した大山は、このように美しい言葉を発見した。大山の勝負観は、この一言に尽きている。
「あの二人は天才ですよ。僕らがどんなに新戦法を案出しても、つぎの対局のときは、それが改善されて相手の得意の戦法と変ってしまっているんですからね」
いくたびか大山に戦いを挑んだ二上達也(九段)は、こういって嘆息する。
二上も、加藤一二三(九段)も、山田道美(九段・故人)も、いま以て打倒大山の夢は果すことはできないでいる。
「内弟子生活の苦労をして肌で将棋を覚えた自分らは、頭で将棋を覚えた若い人に、簡単に負けるとは思いませんね」
昭和35年、若き加藤一二三が名人戦の挑戦者となったとき、受けて立つ大山は珍しく闘志をむき出しにしていい切った。
自信というものであろう。その自信の強さに私は驚いた。
その大山は、騎士の絶好調というのは体力的な面から見ても、36、7歳までだという。その「定年」をとっくにすぎて、なお第一人者たり得るのは、大山が強すぎるのか、若手がだらしないからなのであろうか。
いま、注目したいのは21歳の中原誠七段(名人)である。19も年若い大山が木村義雄から王座を奪ったように、ふた廻り若い中原が大山を王座から蹴落とすのではないか。私はそう予測する。失礼をも顧みず、私は中原の将棋を大山に問うて見た。
「戦後の人では、中原君の将棋は本ものですよ。自分らと同じ感覚です。本当に将棋を知っているという感じがします」
率直に、中原の将棋を評価した。名人を取られるとすれば、「中原君に、でしょうね」とも語っていた。
その通りに歴史は書き替えられて行った。名称は、名称の心を知るとでもいおうか。大山の目のたしかさに、いまさらながら感心した。
90ある名人戦の思い出 -2015.08.01-
名人戦は第三局を終ったところである。
第二局は大阪府下の羽衣荘に転戦した。対局者は、東京から飛行機でやってきた。挑戦者の二上達也八段(九段)は、飛行機に酔って気分が悪いとかいっていた。
対局の前夜、私は朝日新聞学芸部(大阪)の吉井栄治さんと対局室を検分した。旅館のお神さんが、女中さんたちを指揮して準備を進めていた。
その旅館も鉄筋の建物が建ち並んで、十年前の木村・大山戦のころの面影は全くなくなっていた。ただ、対局室だけは十年前のままであった。主人も、戦後の将棋史を書き替えた木村・大山戦が行われた部屋に愛着があるらしく、少しの改造も加えていなかった。
主人は夜遅く、懸軸も十年前に使った狩野常信の三幅に取り替えさせた。お神さんにいいつけて、金庫のなかった古い中国の玉の香炉と、桃山時代の作という根来の花台を出させた。そのことは観戦記にもちょっと書いた。心根が嬉しかった。常信の三幅は、おぼろけながら記憶にあった。盤も、十年前に使用したものである。対局室の設営は、至れり尽せりであった。
第二局も、二上は惜しい将棋を失った。対局が終って、一緒に風呂に入った。湯船に身を沈めて、二上はいった。
「こんな将棋を負けるようじゃ、しかたがないですね。どうにも、だらしなくて・・・」
その夜、大山は飛行機で帰京した。私は二上と一緒に汽車に乗った。「2二玉は、勘違いでした」と汽車が走り出したとき、ウイスキーを呑みながら、ぽつんといった。東京に着くまで、時おり、思い出したみたいに「手」のことを語った。いつもは無口な人なのに、好局を失って口惜しいのか、常よりも多弁であった。
つぎは、鳥羽に転戦した。二連勝をつづける大山は、余裕たっぷりに見えた。二上は緊張していた。第三局も、善戦むなしく敗れ去った。
「ついてないんですよ。つきも実力のうちですからね」
帰りの汽車のなかで、将棋については、その一言しか耳にしなかった。どうして三連敗するのか。実力からいって、どうにも解せぬことであった。
第二局と第三局についていえば、すべては大山のペースで進んだ。食事も、寂しがり屋の大山の希望で会食した。指掛けの夜もマージャンをした。それも大山の音頭取りであった。二上は何一つ、自分の意見はいわない。食事の注文をきいても特別に好みをいわない。寝る時刻まで関係者に付合っていた。
二日目の朝は寝不足らしく、欠伸を噛み殺していた。大山は、「よく眠ったな」と艶のいい顔で笑っていた。
十年選手と、初出場の新鋭との違いであった。経験の差。そうしたところに、二上の敗因があった、と私は思っている。
ある時機、私は二上と同じ多摩市に住んだことがある。時おり、帰りの電車で一緒になることがあった。そのとき、一つの発見をした。
電車が聖蹟桜ヶ丘駅に近づく。私は立上る。二上は悠々と腰を掛けている。電車が停り、自動ドアーが開くと、やっと腰をあげて下車する。いつも、そうであった。
マイ・ペースでゆく。それが二上達也の流儀である。それを知ったのは、名人戦を観戦してから十数年経ったころであった。