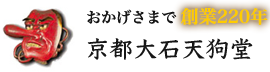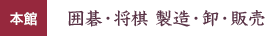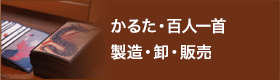将棋の豆知識13〜14 光風社 将棋101話 転用
13 両刀使い-2008.11.01-
将棋を指す人で、碁も強い人がある。当代の一流棋士である大山康晴名人も升田幸三九段も、共に、碁はアマチュア六段である。六段といっても、アマチュアのなかでは、ずば抜けて強い。
以前、両人が名人位を争っていたころ、何かの折りに碁で対戦したことがある。余技の碁でも、この二人は「勝負」ともなれば、真剣に争って譲ることがなかった。
将棋と碁は、兄弟といわれる。たぶん、江戸時代に寺社奉行の支配に属し、同じように江戸城の黒書院で御城将棋(御城碁)を披露した間柄だったからであろう。玉を「詰める」勝負の将棋と「地」を争う碁とは、本質的に異ったゲームなのでなかろうか。私は将棋は指すのに、碁のほうはとんと苦手である。
江戸時代、将棋方は「将棋役」として幕府の職制に組み入れられていた。正式な役名をいうよりは、将棋所といったほうが通りがいい。
その将棋所の起りを調べているうちに、実は碁の本因坊が、その先住者であることを発見した。
『本因坊家伝』には、
———この時大橋宗桂と云者出、将棊を能致により、此時将棊を宗桂に譲り、算砂は碁計になる・・・。
という記録がある。
記録にいう「此時」とは、いつをさすか、どの文献も明示しない。私の解釈では、宗桂が家康から「五十石五人扶持」をもらった慶長十七年(一六一二)に、算砂から将棋所を譲られて一世名人(実際は上手という名称)を唱えた、と見るのが自然のように思う。
算砂は、碁の第一人者であり、将棋所をも兼ねていた人だから、将棋でも第一人者であった。門下の宗桂が、ぐんぐん力を伸ばしてきて、ついに算砂を越えてしまった。だから、算砂は、将棋所を宗桂に譲ったのではないだろうか。
慶長のころ、算砂と宗桂は家康や、秀吉の跡継ぎであった秀頼の前で将棋を披露した。二人の手合は「対揚」と書かれている。現代語でいう「平手」である。
これまで、現存する最古の棋譜は慶長十三年正月二十八日、秀頼の前で両人が指した将棋と伝えられてきた。刊本では、それが一番古いが、古棋書の蒐集家で研究者であった故西村英二は、古写本『将棋集』のなかに慶長十二年の対戦譜があることを発見した。
まさにその通りで、いまでは慶長十二年の対戦が最古の棋譜ということとなっている。
そのころは、両人とも振り飛車で指した。四間飛車も、相振り飛車も見える。慶長十三年の実戦譜は、後手番の算砂は向い飛車作戦を用いる。草創期にあっては、振り飛車は先端をゆく新戦法であった。
二人の対戦で棋譜を伝えるのは八局あり、宗桂が七勝一敗と大きくリードを奪う。算砂が両刀使いであるように、宗桂も碁に堪能であったはずだ。どうしたわけか、宗桂の碁の対戦譜は一局も伝えられていない。
『坐隠談叢』は、宗桂は、「寛永十一年甲戌三月九日卒す、享年八十九歳」と書く。没年は正しいが、「ベールを脱いだ宗桂像」で書いたように、享年は八十歳、弘治元年の生れである。
14 似たはなし-2008.12.01-
囲碁には『坐隠談叢』という囲碁通史がある。明治三十七年刊。末開拓の将棋史に鍬を入れるとき、参考にと思って読んでみた。労作ではあるが、私には余り参考にならなかった。所詮、自分で史料を漁るよりほかに道はないと思い直した。
将棋に比べて、囲碁の歴史は古い。ルールも変っていないので、平安時代や鎌倉時代のことを調べるにも、多種の古将棋群を先史として持つ将棋ほどには困難は感じない。断簡零墨のたぐいも多い。
将棋史を研究する私は、同時に、囲碁史のほうも調べて見た。断簡零墨のなかには、囲碁史のこととも将棋史のこととも受取れる似た素材がいくつかみつかった。
囲碁史では「棋」を囲碁と解するらしい。いまでも紛らわしいが、「棋」は、時には囲碁を、時には将棋をさしている。紛わしい「棋」の用語から、歴史が混線する場合もあった。
また一つには、贔屓という気持も手伝って、面白い素材は、わがほうに引き寄せて用うるという傾向もあったらしい。
「爛柯」という言葉がある。
晋の時代のことである。木こりの王質という人が、四人の童子らが碁を打っているのを、貰ったナツメを食べながら観戦していると、飢えを覚えなかった。しかし、その間に、斧の柯が爛り、帰ってみれば、当時の人はだれもいなかった。
その故事から、「囲碁にふけって時の経つのも知らぬこと」をさし、転じて、「遊びに夢中になって時の経つのを忘れる」という謂になったが、いまでも爛柯は、「囲碁」の専用語として罷り通っている。
ところが、その「爛柯」についてさえ、異議を唱えるほどに熱烈な将棋ファンが江戸時代にはいた。
幕末、儒者として名の高かった朝川善庵は、片山兼山の第三子である。嘉永二年二月七日、六十九歳で没した。翌三年七月、和泉屋金右衛門から上梓されたのが『善庵随筆』二巻である。
冒頭に、「玉将説」を掲げ、大橋本家十代目宗桂よりの聞書として、「玉将」が正しく、王将が誤りであることを実証した。将棋史のうえでは、大そう貴重な資料である。
将棋史の考証に熱意を燃やした若き日の幸田露伴は、「玉将を王将とするの非なることは、まこと善庵の説の如し」と讃えている。
その善庵は、同じ随筆集で、「爛柯」の故事は、囲碁のことではなく、「童子四人が琴を鼓するのを見る」というのが正しい記述だと主張する。だから、「碁ノ典故ニハ引用シ難ク思ハル」と書き、さらに、牛僧孺の『幽怪録』には、「相対して象戯し」とあるところから、「爛柯」の故事は、「碁ニハアラズシテ、象戯ナルコト論ヲ待タズ」と自信を以て結論づけている。
善庵の論旨を弁護することも、論破することも私にはできない。中国の古典を繙いたとしても、判定を下す学殖はもとよりない。ただ、善庵の説を読んで、いささか牽強附会の感を抱く。将棋ファンらしい「好意」は謝するとしても、「爛柯」の故事は碁に譲りたい。
目角を立てるほどのことではないと思う。