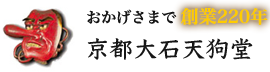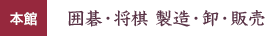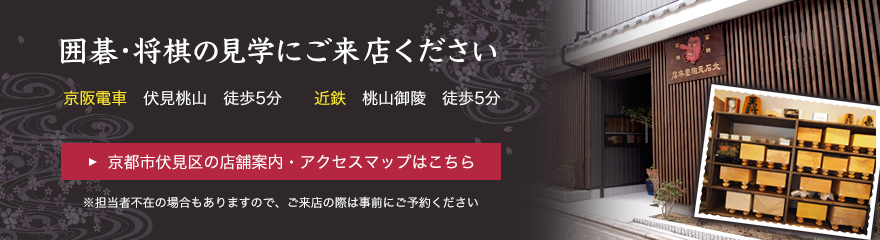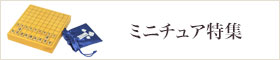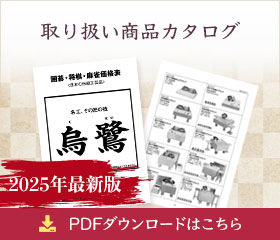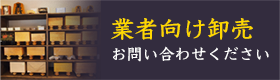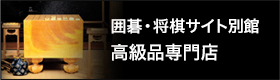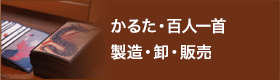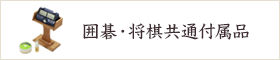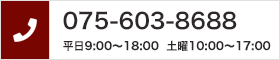将棋の豆知識21〜22 光風社 将棋101話 転用
21 香車をヤリという-2009.07.01-
将棋の駒の名称は、言語学者の故金田一京助博士も説くごとく、玉、金、銀、桂、香というふうに珍宝佳品の形容がついて美しくなっている。
なかで、金と銀とは、商売に縁の深いところから、江戸時代は、そちらのほうで重宝されて、文芸作品にもしばしば顔を出すようになった。
香車は、そうした分類からすれば、花柳界に縁のある駒ということができる。
歌川国芳(文久元年没)は、「香車の駒」と題する錦絵を描いた。花魁が右手に香車の駒を持つ。美しいエロチシズムを漂わせる構図である。
香車は俗に、槍と呼ぶ。盤上を一直線に進むその性能が、鎌倉末期から戦国時代にかけて合戦の主力であった槍の威力に似るとこから、そう呼ばれたのであろう。
その槍を片仮名で「ヤリ」と書くと、転じて男性の象徴という意味となる。花柳界に縁づいたのも、そうした因縁がなさせたものであろうか。
『洞房語園』には、「鑓手、古来名を花車といふ。花に回るといふ意か。然れども、くわしやと呼ては聞へあしきとて、香車と香かへたり、香車は将棋の駒の一つなれば、香車と呼ばずして、やりといひふれたり」と、その由来を記してある。
花柳界では、やり手婆のことを花車といったが、「くゎしゃ」では発音がよくないので、「香車」と書きかえたという。異説もある。花車は、「火車」のことであって、「つかむ」という意味を持つ。この場合の「つかむ」は隠語であって、女郎を買うというほどの意味であったらしい。
いずれが、ヤリの語源であるのか、私は断を下すことはできないが、いずれにしても、
やり手 花車 やり
という流れをたどって、そうした俗言が生れたようである。
日光の興雲津院には「将棋堂」がある。
興雲津院は、寛永年間に寛永寺御学問所の本尊を移して建立した。御堂は、大黒天、毘沙門天、弁財天の三体を合祀して、「三堂」と呼ばれていた。
ところが、明治の初年ごろから、参詣人が安産の祈願をこめ、満願の礼に将棋の駒を奉納して、いつしか、「将棋堂」とか、「駒堂」と呼ばれるようになった。津院は、もと安産の祈祷所であって、妊婦は境内の土を踏むだけで安産の願いが叶えられるという伝えがあった。
満願の礼にと奉納する駒は、どの駒と種類は決められていないというのに、見れば、香車の駒が群を抜いて多いのは、どうしたわけなのであろうか。
古川柳に、香車を詠みこんだ句が一つだけみつかった。(『誹風柳多留拾遺』八編3)
香車先つくやうに出す柳橋
柳橋は、神田川が隅田川に流れこむところにかかる橋。このあたりは船宿が多い。岸にはたくさん船がつないである。そのなかを巧みに、勢いよく船を漕ぎ出してゆく。
ゆく先は、吉原であった。
【後記】法政大学出版局の『将棋』という本の口絵に、「香車の駒」と全く同じものが掲げられているが、これは大塚工芸社の複製版で、古色を出すために筆者が細工を加えたものである。
22 香車の差物-2009.08.01-
戦国時代の笑話を集めた策伝和尚の『醒睡笑』巻一「落書」の部第26に、香車を詠みこんだ狂歌がある。
—妙心寺の僧に、金蔵主といふあり。賀茂の競馬を見物に行き、帰りに印地のある所にて、負くる方を贔屓し、強み過ぎ鑓に突かなければ、
五月五日競馬帰りの金蔵主
鑓に突かれてひしやとこそなれ
端午の節供の日は、賀茂競馬の見物くずれが、三条河原などの印地打(石合戦)の弥次馬に加わって、騒ぎを大きくした。
狂歌は、鑓(香車)と飛車(びしゃつぶれの秀句=洒落の句)の取合せである。香車が文芸作品に登場する最初ではないかと思う。
香車は勢いよく走るところから、戦国武将たちにも愛されたらしい。永禄十二年(一五六九)十月、武田信玄が小田原城に北条氏康を攻めたとき、信玄若衆の初鹿野伝右衛門は、白地に「香車」のニ字を墨書した差物を風になびかせて出陣した。
同月六日、信玄は敵城に攻入ることを期し、すでに本陣を酒匂川近くに進めていたが、ふと、若衆の指物を目にとめて不興気にいった。
「香車は進むを知って退くを知らぬではないか!」
そこで若衆を呼び寄せて、懲罰の意味をこめて瀬踏の大役を命じた。伝右衛門は直ちに馬を駆って激流に躍りこみ、見事に大役を果たした。ほどなく復命に戻った若衆の背に、依然として「香車」の差物がはためいていた。信玄は、功を賞するばかりで、差物については、ついに一言も発しなかったという。
戦場では、香車の差物は人気の的であったらしい。紀州藩では、香車をも含めて十九種の差物は、由緒ある者のほかは、みだりに用いてはならぬという軍令があった、と『南紀徳川史』に誌してある。将棋の駒の差物は「駒金」と呼ばれている。いずれも、香車を用いてある。
下って、明治元年(一八六八)の上野戦争のときにも、香車の差物が活躍した。
五月十五日、上野の寛永寺に立籠る彰義隊に対して、大村益次郎の率いる官軍は猛攻を開始した。この戦いは、午前中に呆気なく終って、彰義隊は潰走した。
彰義隊の複隊長は、上州甘楽郡磐戸村の名主の次男坊で、暴れん坊の天野八郎である。将棋が大好きで、「戦場でも将棋を指すんだ」と、香車の二字を旗印とした。
前進あって、後退を知らない。その心意気を香車の二字に託して出陣したというのに、新兵器の大砲の前では、香車の旗印も意気が上らなかった。
元禄時代の人、各務支考は、俳文の『将棋の賦』で、それぞれの駒を面白可笑しく描き出し、香車のことは「外様の小姓」に見立てて、
—しかるを一陣に進む時、歩兵の算用を仕ちがへて、ひしと鑓先を止められたれば、こなたよりひかへて為べかりしものをと、此の後悔は若気のいたりともいふべし・・・。
香車の暴走を「若気のいたり」と評するあたり、いいえて妙というべきである。