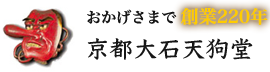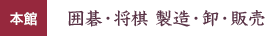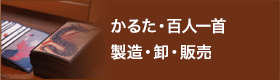将棋の豆知識45〜46 光風社 将棋101話 転用
45 桂馬の高とび-2011.7.01-
日本の将棋は、桂馬という駒の性能が加って、ぐんと面白くなっている。桂馬は、使用よろしきを得れば妙味を発揮する。反対に、策なく飛出せば、「桂馬の高とび歩の餌食」という惨めな報復を受ける結果となる。
桂馬は、両取りの性能を持つ。「桂馬のフンドシ」と呼ばれて、江戸の文芸には欠せぬ主人公であった。
落語に、「鼻の上の桂馬」がある。
—どうしても、かぶり物をとらない源さんに、わけをきくと、毎日エビス様に福をくれるようにと参詣したところ、一週間目にエビス様が現れたので両手を差出すと、両の手に一枚ずつ小判を呉れた。然し、甲子年のエビス金といって、使えないんじゃないかと心配した途端、二枚の小判が額にくっついてしまって取れない。それで、かぶり物をしている。
「ほほう、妙なことがあるもんじゃな。見せてごらん。おお、これはエビス金どころか結構な慶長小判だ。ほんとの金だよ」「えッ、ほんとの金ですか、どうしても取れませんかね」「二枚はむずかしい。一枚なら取れる」「一枚でも結構です。どうしたら取れますか」「鼻の上へ桂馬を打て」・・・。
「戎小判」とも、単に「桂馬」とも題して、柳家小さん師匠が演ずる。元禄十年(一六九七)に京都で開板した『露鹿懸合咄』の「念仏請」が原話。話の筋は、原話とは異るが、上方種といわれる。
サゲは、小判の金と将棋の駒の金とをかけたものである。「エビス金」とは、分配できない余り金のことをいう。
川柳になると、さらに、その両取りを活用して、色事の世界に飛びこんでくる。
かの後家に和尚桂馬とうたれたり(拾遺二編13・明和中)
「後家」は、川柳では格好の題材となる。同じように、「和尚」は、その隠し妻が大黒といわれるように、好色家の代名詞として登場する。
手にあらば桂馬うちたき姉妹(拾遺三編9)
若殿の遺ふ桂馬は鼻が利き(拾遺八編27)
いずれも、桂馬の性能を活かした句であるが、あとの句で、思い出すことがある。
蕉門の十哲の一人に挙げられる各務支考の俳文、『将棋の賦』は、玉以下の駒の性能を駆使して美文を綴る。桂馬の条では、「ここに桂馬こそをかしきものなれ、進む時は物の影より飛び出でて危きに臨みて退くこと能わず、さるは猪の勇気に以て、鼻のきかざる殊にをかし」と書く。桂馬は、「鼻のきかざる」という伝えがあって、投句者はそれを詠みこんだものであろうか。
めつかちの蛙桂馬にとんで行き
この句は、初代の柄井川柳の作と伝えられる。大阪に住む石井縞胤宗匠から、この句のあることを教わった。
その後、宗匠とは賀状のやりとりがある。まだ、お目に掛らぬのに、私の記憶のなかでは、知己となっている。
いく人か将棋を通して、そうした知己がいる。
46 景物歌仙-2011.8.01-
川柳の作品の構造は、大別すれば、「縁語」「洒落」「地口」「見立」「並列」「取合せ」「暗示」「言葉つかい」「数字利用」「文句取り」の技巧に類別できるという。
ここで紹介したいくつかの作品も、構造的に見れば、上に示した技巧を踏まえて作られてある。投句者は、無知の階層もあれば、当時のインテリもあった。そうした投句者にとって、作品のお手本は、初代・柄井川柳の作品であったはずだ。
『誹風柳多留』の二編(明和四年刊)には、末尾に、「景物歌仙」と題して歌仙三十六句を載せ、編者の呉陵軒可有の序文が添えてある。
—当世の前句(現代の前句附)ハ誹諧の足代(足懸り・準備工作)ともならんや。よつて六々の吟(歌仙三十六句)に、川叟(柄井川柳をあがめた言葉)数としこのめる(数年間に選んだ)景物(俳諧用語・四季折々の事物)を掻集め結ぶ(歌仙のなかに詠みこんだ)といへども、同様の景物多きゆへ、輪廻(俳諧用語、打越ともいう。附句に用いてよいが、それを一つ越した次の句に用いるのを忌むもの。露に対して雨・露のたぐい)遁れざる所は見ゆるしあれかし。此道(俳句でなく、前句附)熱心のかたへ景物を騙し知らすのみ。
序文は、川柳を研究する上では面白い材料であるが、編者の狙いは、初代川柳の選句の傾向を示したものといわれる。三十六句は、その形式は連句の規制を守っている。
いささか、むずかしい議論になったが、要するに、投句の手引きである。選者の初代川柳は「古今独歩といわれる選句眼を持った人物」であったから、投句してもボツにならないためには、これくらいのことは知っておく必要があったのであろう。
なかに、将棋の句が二つある。(—傍線は景物の題目を示す)
悶象戯ぐれんかへして歩を尋
「悶象戯」は、もつれた将棋の意味。「ぐれんかへし」は、「ぐれかえし」の謂で、ひっくり返すこと。
将棋がもつれて、一歩あれば勝つ。「いや、たしかに一歩あったはずだぞ」と盤をひっくり返して、駒の行方を尋ねる。よくある光景である。
髪そよそよと凄い山伏
前句の将棋を指す「人」に着目した附句である。もつれた将棋に双方が熱中して、目をぎらぎらさせる。髪も乱れて、すごい面相となっている。それを「山伏」にたとえる。
初代の柄井川柳は、どこまでも選者に徹して自らは一句も作らなかったことになっている。選者として、厳として聳え立つための方便であったのだろうか。「めつかちの蛙桂馬にとんで行き」の句が、川柳作と伝えられるのも、そのためである。
寛政二年(一七九〇)九月二十三日、七十三歳で宗匠は没した。以後、川柳は本文の文学性を失って、しだいに「狂句」の世界に墜ちて行った。