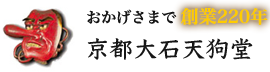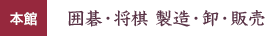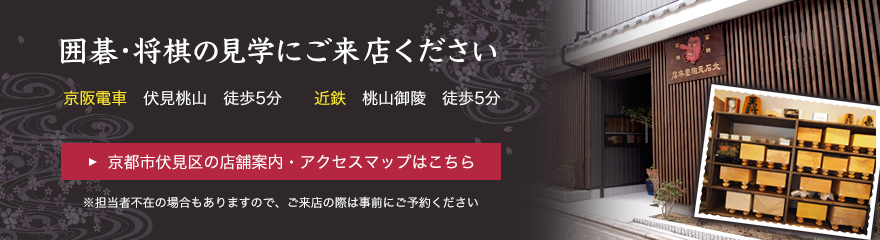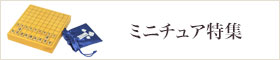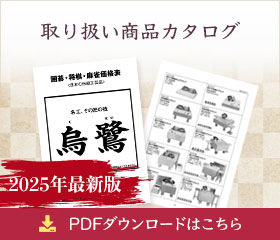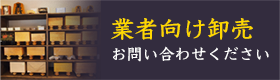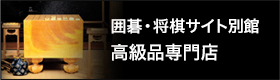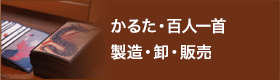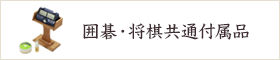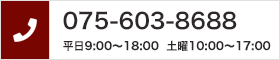将棋の豆知識75〜76 光風社 将棋101話 転用
75私の免状 -2014.05.01-
長く観戦記を書く仕事にたずさわるせいか、世間ではかなり将棋が強いように思われている。ほんとうは、せいぜいアマチュア初段ぐらいである。
もう、だいぶ以前のことだが、将棋道場の看板を見て飛びこみ、二級の人に軽くひねられた経験がある。あのころよりは、すこしは強くなっているので、初段くらいはあろうかと自己診断している。
ふだん、将棋を〈観る〉ことは多いのに、〈指す〉という機会はすくない。一年に何回かは、先輩の作家たちと将棋会を催す。優勝すれば、リボンに名前と生年月日を書きこみ、それを優勝カップに結びつける。この会が始って以来、幸運にも優勝を飾ったのは一回きりだ。序盤は下手だと思う。駒がぶつかりある中盤ともなれば、すこしは手が読めるようになる。アマチュアは、強豪をのぞけば、たいていは私は同じ悩みを持つらしい。
プロの先生には、二枚落ちで随分と御指導を願った。二枚落なら、何とか勝負になる。しかし、大駒一枚を加えられると、とたんに下手が動けなくなってしまう。プロの底力を知っているので、闘志がわかないという理由もある。
自己弁明はさておき、こうした実績から見ても、まずは初段クラスというのが順当であろう。
ところが、将棋連盟発行の『有段者名簿』には、堂々とした三段として名を連ねている。先日も、この名簿を御覧になった近隣の方から電話で挑戦を受けて戸惑った。『将棋世界』の二段コースで、みごと二段を獲得された方だそうである。
「実は、三段は名誉段でして・・・」
電話口で汗をふきふき、いま書いたように、いかに実力は三段に値しないかと例を挙げて説明した。
「将棋史のことなら、多少は・・・」
こうつけ加えると、先方は何人かがいたらしく、電話口で相談している。
「将棋史の研究家なら、そうかも知れんよ」
若い人の声である。
「そうなんですよ。実戦はあまり強くないのですよ」
「しかし、観戦記を書くほどだから」
「ああ、あれは、いつも弁解していますが、プロの解説を受けて書くのです」
やっと、お引取を願って胸を撫でおろした。
受話器をおいて、久し振りに巻物の免状を出して見た。三段の免状は昭和三十三年二月三日の日附がある。時の会長、名人、十四世名人お署名がある。ただ、ちょっと変っているのは、そのあとに十名の署名が並んでいることであろう。
大山康晴、塚田正夫、五十嵐豊一、花村元司、灘蓮照、原田泰夫、二上達也、坂口允彦、大野源一、丸田祐三。
クイズめくが、なぜ、この十人の棋士に署名していただいたのか。棋界通の方なら、このとき、この十名の棋士はどんな地位にいられたか、お察しがつくことと思う。
十五年前—昭和三十三年は、短時間制の〈早指し王位戦〉があって、私はそれを担当する記者であった。そのころには、升田さんが名人である。記憶に間違いなければ、大阪で新聞記者をしていたころの旧友が免状を貰った。
「ついでに君も・・・」
というわけで、三段の免状を戴くことになった。三段というのは、「将来三段ぐらいにはなるだろう」という先附小切手のような意味であったらしい。
いま以て初段の域に留っているのは、甚だ申訳ない。
76私の玉将説 -2014.06.01-
玉が正しいのか、王が正しいのか。とっくに『玉将説』が正しいことになっているのにときどき、議論のむし返しが出てくる。
理論的に正しいのは「玉将説」であり、「王将説」はたぶんに政治性を加味した議論である。といって、「王将説」を裏づける決定的な文献はない。議論のむし返しが起るのも、そのせいであろう。
そこで、一応は古から伝わる文献を整理しつつ、その可否を考えて見ることとする。
朝川善庵は江戸の人。松浦候の儒官で、文化十二年に下田に清国の船が渡来したとき、招かれて通訳をした。善庵の父は片山兼山。この人も将棋好きな学者で、荻生徂徠が創作した『広象棋譜』に序を寄せている。
善庵は、十一代大橋宗桂と親交があった。文化十一年に宗桂が実戦集の『将棋明玉』を出版するに際して、乞われて序を付した。その序のなかで、善庵は「玉将説」が正しいことを立証した。
—予先年大橋宗桂ノ儒ニ応ジテ、其著述セル将棋の書ニ、序スルコトアリシニ、王将トイフ馬子ハ、何トモ疑シキ名ナリ。王ナレバ王、将ナレバ将トイフベシ。王ト将ト混称スルノ理アルマジト。将棊の諸書ヲ攷証スルニ、開祖宗桂ヨリ、四代目宗桂マデ、代々著述スル所の将棊図式ニ、雙方トモ玉将トアリテ、王将ノ名ナシ。因テ思フニ玉ヲ以テ大将トシ、金銀を副将トスルナルベシ、左スレバ、金将銀将ノ名モ拠アテ、ヒトシホ面白ク覚ユ。蓋シ五代目宗桂以後、雙方ノ同ジク紛ハシキヲ嫌ヒ、一方ハ一点ヲ省キテ、差別セシニアラント・・・。
初代宗桂このかた、四代宗桂までは、図式には「玉」を書いた。五代宗桂の代から、それでは紛らわしいというので、一方を「玉」とし、他方を「王」と書く習慣が始った。
—今ノ宗桂ニ語リシニ、宗桂曰ク、ソレハ必ズ然ルベシ。其ワケハ毎年十一月十七日、御吉例ニテ、御城ニ於テ将棊仰セ付ラレ、其図譜ヲ上ルニ、雙方トモ玉将ト書スルコト先例ニテ、王将トハ云ハヌコトノ由、家ニ申伝ヘ、今ニ代々玉将ト書上レドモ、何故トイフコトヲ知ラザルニ、コレニテ明白トナリト。遂ニ嘗テ著述セル書ヲ、将棊明玉ト、名ヲ易ヘ上梓シ、予ガ序ヲ巻首ニ載タリキ・・・。
御城将棋の棋譜書上げの際には、両方とも「玉」と書くのが例であった。それは、将棋家の申し伝えである。いまに残る『御城将棋留』(国会図書館蔵)も、「玉」を用いている。幸田露伴も、考証のすえに「玉将説」をとるに至った。善庵の説をよしとし、さらに、
—王の字の横の三画の中の一画上に近きものは帝王の王の字にして、横三画相等しきものは珠玉の玉の字なれば、今の将棋の馬に、一方の玉と書して一方を王と書せるも過誤ならず、ただこれを玉将と呼ばずして王将と呼ぶは過誤なるのみ。今の棋聖小野氏の如きは常に玉とのみ呼びて未だ曽て王と呼ばず。これ其正しきを失はざるものといふべし・・・
昔は、王という字も横の画の書き方で、玉と読んだり、王と読んだりした。だから、一方の駒が、「王将」となっているといっても、それを「おうしょう」と呼ぶのは誤りである。
金田一京助博士も、駒の名称は、「玉、金、銀、桂、香と珍宝佳品の形容が附いて美しくなっている」と説く。将棋の発生から見ても、「玉将説」が正しく、私は「玉将説」を是とする。
そうした説を知ったうえで、便宜的に、玉と王との区別をつける現行のしきたりは、私も認めているわけである。