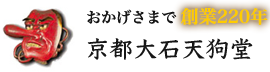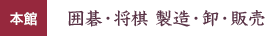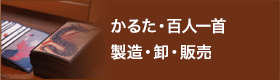将棋の豆知識85〜86 光風社 将棋101話 転用
85明治棋界の回顧談 -2015.03.01-
関根金次郎の一番弟子であった土居市太郎(名誉名人)は、昭和四十八年二月二十八日、八十七歳の長寿を完うした。
その三年前、棋界で初の勲四等瑞宝章をうけ、東京・大手町の産経会館で祝賀会を催した。入場料は二千円。祝賀会を有料で催すのは初めてのことである。数多い門下生が師のために奔走して、広い会場は満員という盛況であった。
頼まれて私は、裏方として手伝った。「名騎士・名勝負」と題して、その一代を映写で再現した。NHKの三上規アナウンサーが朗読する一代記を私が書き、そのうえ、劇場の映写室で生れて初めてスライドの操作をした。
一代記の草稿は散逸してしまった。笈を負うて上京する苦心談は、別に、その日のパンフレットに「回顧談」として書いた。
関根師と師弟の約束を結んだ土居青年は、青雲の志をいだいて故郷をあとにした。明治四十年、二十歳である。
神戸で高段棋戦を見てから、東海道各地を二、三日泊りで漫遊した。漫遊といっても、実は、旅費を稼ぎながらの辛い旅である。四日市で井上義雄八段に一丁半で二番教わった。二番とも「金開き」であっさり負かされてしまう。観戦していた小菅剣之助(のちの名誉名人)は、
「土居は定跡を知らんのう」
と笑った。土居は言葉に詰った。定跡のなんたるか、知らなかった。つぎの日、小菅は天野宗歩の名著『将棋精選』三冊を与えた。土居はむさぼるように読んだ。
大磯で師の紹介状を持って、パン屋の某氏を訪ねることになっていた。メリケン袋に衣類や将棋本を入れて担いでいた。駅の改札口を出ると、すぐに巡査につかまって、不審尋問を受けた。
「本は進物したり、望む人におわけ申そう」
と説明したが、なかなか聞き入れてくれない。本署まで出向き、やっと怪しい者ではないとわかって釈放。当時は、棋士という職業は、なかなか世間の人には理解してもらえなかった。
横浜のクラブに一、二ヶ月滞在して東京に出た。日本一といわれる関根師ですら、自分の家を持っていない。上京して二年ばかりは、住むに家なく、将棋の勉強よりも、生きてゆくということが最大の課題であった。明治四十二年『将棋同盟社』が生まれ、どん底の棋界にも一条の光明が射しはじめる。関根師は、やっと佐久間町の牛肉屋の隣に家を構え、一番弟子の土居青年は、玄関番から女中の役まで仰せつかった。
明治四十三年、四段。『二六新聞』がはじめて棋戦を催し、土居四段は先鋒として出場した。勝ちまくって二十一連勝。二十二人目はもう相手がいない。この間、一年。『二六新聞』は、土居四段の強さに舌を巻き、とうとう棋戦を打切ってしまったという。
「新聞将棋のない時代は哀れじゃった」
土居名誉名人は、「—いまの棋士は幸せじゃて。先輩と戦いながら勉強ができるんじゃから・・・」と、しみじみと語っている。
晩年の翁とは、ことのほか親しく付き合い、賀状も戴いた。昭和四十七年の賀状は、「明示廿年生の老人、お陰を以て元気に新春を迎えました」と書いてあった。つぎの年は、代筆であった。あとで、病状が悪化して入院したことを耳にした。
86銀が泣いている -2015.04.01-
将棋を知らない人でも、映画や芝居の「王将」で、坂田三吉の名は御存知であろう。
坂田三吉は、戦後に死んだ人であるのに、早くも伝説の人となっている。奇行が多かったせいか、生存中から、すでにして伝説の人であった。
目に一丁字もなく、天下を風靡した独特の坂田将棋は、その才槌頭から産み出されたものであった。その着想が、現代将棋の骨格をなすと高く評価したのは、升田幸三九段である。形は力将棋に見えて、その構想には余人を寄せつけぬ新しさがあった。
掛値なしに、将棋の天才であった。
映画や芝居で有名になったのは、「銀が泣いている」という台詞である。あの台詞は、劇作家北条秀司氏の創作である。映画のその場面の局面は、監修に当った升田さんが創作した。升田さんから、そのことをきいた。妻の小春も、本名は「こゆう」という。
「銀が泣いている」の台詞は創作であるが、それに似た話はある。大正四年に上京して、井上義雄八段と戦ったとき、中盤戦で坂田の銀が立往生して苦戦に陥った。
一日目は指掛けとなって、旅館に戻った。翌朝、観戦記者の桑島鈍聴子が迎えにゆくと、「わての銀が泣いているよって、この将棋はあかん・・・」
と浮かぬ顔をした。一方の井上は、勝ち将棋だと自慢している。何気なく鈍聴子は、そういった。
「ほんまでっか?」
坂田の目は妖しく輝き出した。二日目の対戦で、非勢を盛返して坂田は、もののみごとに井上も討取った。
坂田三吉と親しかった金易二郎名誉九段は、そのときの坂田の心境を代弁して、「相手が勝ちだと油断している。それなら、多少は不利でも、努力すれば希望はあると着眼して気持を取り直して真剣に取り組んだ。それが勝因といえようか」と愛弟子の山本武雄八段に書き送っている。
さらに、「相手が不用意にもらした一言をとらえて、勝ちをおさめたのは、さすが大棋士と、敬服の念を深めた」とも述べている。
上京して市電で宮城前を通ると、「ヘエー、あそこに天子様が・・・」と坂田は甲高い声を挙げ、腰を折り曲げて最敬礼をした。市電の窓から銀行が見えると、「あれ、銀行でっしゃろ」と得意げにいった。
将棋の駒の文字のほかで、坂田が知るのは「銀行」と「品川」だけであった。
そうした奇人振りを抜きにすれば、稀有な勝負師であった。
世間では、プロ棋士のことを勝負師と呼ぶ。私もそう書くが、それを「腹芸」の持主と解するなら、考え直してほしい。
勝負の場で、一瞬に決断を迫られることがある。その勘の冴えは、勝負する人間にとっては大事な才能といえる。ただ、その勘は、一か八かの気まぐれではない。積み重ねた読みの集積の結論として、はじき出される答えである。
勝負とは、端的に申せば、計算することである。対局中、苦戦に陥っても、必ず、チャンスはめぐってくる。大山康晴名人は、「一局には三回はチャンスがめぐってくる。どれを見送り、どれを活かすか、その決断がむずかしいんですよ」という。坂田三吉は、対井上戦で冷静な判断を下してチャンスをつかみ、そこで大胆な勝負手を断行した。偉大なる勝負師であった。