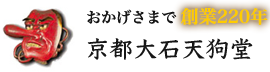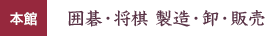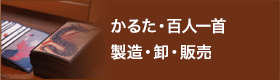将棋の豆知識11〜12 光風社 将棋101話 転用
11 鳴くまで待とう-2008.09.01-
家康は戦国第一の武将であった。戦国第一の行政官であった。将棋に対する見方も、信長や秀吉とは一味ちがって、行政官の冷徹な目でみつめていた。
江戸に幕府を開いたそのころは、戦国生き残りの武将がまだ多くいた。血で血を洗う戦国の荒々しい気性が武将たちを「荒くれ者」にする。戦国武将の側面をなぐり捨て、行政官として徳川幕府の基礎造りに精出す家康は、
「その戦国の血を鎮めるために・・・」
と斯道を「娯楽」として推賞した。将棋がもつ知的ゲームの面白さを回復したのは、家康の代になってからである。
慶長十七年、家康は「碁所衆」や「将棋指衆」に扶持を与えて保護政策をとった。碁の本因坊と同じく「五十石五人扶持」を与えている。本因坊は庶民出身の宗桂とはちがって、「袋入りの長柄は免され乗物は下乗まで御免」という格式があった。
その本因坊と同格の「五十石五人扶持」を与えたのは、将棋方とすれば、破格の待遇である。のちに、寛永十二年に至って、将棋三家の家格は「二十石?人扶持」に落着くが、将棋衆に扶持を与える道をひらいたのは、家康の功績である。
何でも「権現様の御先例」にならう徳川幕府の為政者は、もし、家康が扶持を与える道をひらいていなければ、将棋家の運命はどう変ったか判らない。
その家康は自分で指して愉しむというよりは、主催者として「将棋指衆」を集めて観戦することを好んだらしい。ほんとうは、将棋よりも碁のほうが強く、将棋では勝ち目がすくないので観戦役をきめこんでいたらしい。
「鳴かぬなら鳴くまで待たうほととぎす」型の人物とすれば、じっくり構える将棋を指しただろう。もしかすると、戦国武将のたぎる血汐が胸に宿っていて、そのころ流行した急戦の振り飛車で奇襲を狙ったのではないか。あの「狸親爺」のことだから、緩急自在の指し方をしたように思われる。
『当代記』によれば、伊達政宗は慶長十一年(十二年が正しい)二月八日、家康を主賓として自宅に将棋と囲碁の者を招いている。その日は風が強く、塵埃が部屋のなかまで舞い上る始末で、家康は昼食を終えると早々に引揚げた。当日の会は、将棋ではなく囲碁の会であったらしい。『東照宮御実紀』も、「御消閑にもてあそばれたこともあるが、深入りしなかった」と書いている。
いまに伝える最古の棋譜は、慶長十二年に大橋宗桂と本因坊算砂とが指したものである。後手の算砂は四間飛車で戦った。たぶん、駿府城を修築してそこに家康が隠退したとき、二人を招いて対局させたのではなかろうか。
長子の二代将軍忠秀は、狸親爺を嘆かせたくらいの堅物であったが、将棋は好きで、かなり強かった。慶長十七年三月二十日、駿府に宗桂を招いて観戦したあと、山名禅高を相手に将棋を指したと『当代記』は伝える。
その席に家康もいた。両眼を閉じて眠るがごとく坐りつづけ、対局が済むと、待ち構えていたように室町時代の有名な武将である山名宗全の後裔に酒肴を賜ったという。
食道楽で、人をもてなすことが将棋ファン家康の愉しみでもあった。
12 将棋の殿様-2008.10.01-
古典落語に「将棋の殿様」という話がある。柳家小さん師匠の十八番である。師匠は将棋が強いので、これを演ずるときは、すっかり将棋ファンの顔になっている。
話の筋は、こうである。
わがままな殿様は、苦戦に陥ると、「これ、しばらく待て、控えろッ、その歩を取ってはいかんぞ。その歩を取られては、予が困るのじゃ」と無理難題を吹っかけるを常とした。
負けたほうには、頭を鉄扇で打つ約束事になっているが、負けるのは、いつも家来ばかりで、近習衆の頭はコブだらけである。
病気引籠り中の御意見番、田中三太夫が久々に登城して、「たかの知れたる殿のお手際、おのおの方の敵討を致して進ぜよう」と挑発する。例によって殿様は待ったをするが、三太夫は「いえ、拙者取りかけたこの桂馬、たとえお手討になりましょうとも、決して待てません」と意地をおし通した。
とうとう殿様は負けになり、三太夫が鉄扇で力一杯、殿の頭を叩くと、殿様はさすがに痛さをこらえて、近習衆に向って、
「これ一同、笑っているな。早々に将棋盤を片づけろ・・・。いや、待て待て、焼き捨てろ。明日より将棋を指す者には、切腹を申しつくるぞ」・・・。
講談に、大久保彦左衛門の「将棋の意見」がある。また別説に、初代三笑亭可楽が十一代将軍家斉の前で、この話を演じたともいう。
江戸時代、殿様はわがままで通っている。幕末から明治まで生きて将棋を能くした関澄検校は、殿様と指すときは、決して上手が駒を落とすことは許されなかった、と語っている。
どんなに強くても、殿様とは平手で対戦して、うまく負けて上げることを心がけなければならなかった。それどころではない。対戦中、いつ殿様が機嫌を損じて、お手討の声がかかりはしないかと、
「それは、それは、心配でございました」
と思い出話を伝えている。
ただ、ほんとうに将棋の好きな殿様は、そういう野暮はしなかった。十代将軍家治は、将軍家の者に駒を落されて指した棋譜を残している。関澄検校が出入りしていた津藩主の藤堂和泉守は、駒割の原則をきっちり守って指したという。
和泉守は、明治の代になって将棋界が衰微の極に達したとき、将棋指しを自宅に招いて対戦させ、いくばくかの祝儀を出していた。
大和郡山藩主の柳沢保恵も、明治から大正にかけて、棋界の「影の実力者」として将棋指しの面倒を見た。どうしたわけか、坂田三吉を好いて、小野五平十二世名人の跡を継がせようとはかった。坂田が大正十四年に名人を「僣称」した裏には、そうした後継者の願望が渦巻いていた。
明治・大正のころは、後継者をもたないことには食べていけなかった。好意あるスポンサーにしても、棋界という大きな立場からすれば、功罪相半ばする存在であった。
関西には、「やらず、ぶったくり」という言葉があって、坊さんと将棋指しの名を挙げていた。新聞将棋が生れ、将棋指しが「棋士」に変って、そうした悲しい歴史は消え去った。
遠い昔の物語である。