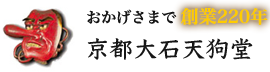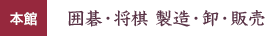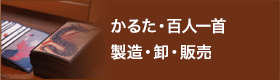将棋の豆知識25〜26 光風社 将棋101話 転用
25 女流第一号-2009.11.01-
文化・文政のころ、大橋浪女が出た。二段というだけで、経歴は判らない。大橋という姓から、将棋家の大橋家にゆかりのある女性だったかも知れない。
文化六年(一八〇九)四月、七段の福島順喜と飛車落で対戦して、一〇二手で勝った。中・終盤がしっかりしていて、なかなかの強豪と見受ける。棋譜が伝えられることが有難い。それゆえに、この浪女に、「女流棋士第一号」なる称を私は進上することとする。
つぎに名乗り出るのは、池田菊女である。
この女性は、話題が多い。話題になる振舞いも多かったらしい。『将棋営中日記』には、初めは、「芝神明前のあやしき女」として登場する。十世名人伊藤宗看の三男坊で、放蕩のゆえに勘当された金五郎と交りがあったことから、よからぬ噂を立てられたものであろう。
のちには、「銘酒屋の娘の由にて、至て将棋熱心の由」と、その身分が訂正されて、菊女は名誉を回復した。
天保十一年(一八四〇)、山王無量院で催された将棋会に出席して、七段大橋宗桂(飛車落)と松波瓢斎(角落)との席上手合せを披露した。
—神明前に住居せし池田菊女と云へる者、子九月廿二日岡村幾次郎四段の開会の節に、男計りの中へ只一人出席せし由、誠に珍敷事のよし、其様子人を人とも思はず、其の上早き将棋にて、考えもせずにさすよし、当時初段のよし・・・。
と『将棋営中日記』の筆者は、驚きを以て綴っている。そうであろう。そのころの男性の目からすれば、菊女の行為は驚き以外の何物でもなかったろう。流行の瓦版にも、菊女のことが出て、人気者となったのではないか、という想像もしたくなってきた。
菊女は明治の世まで生きた。明治三年の将棋番付に、四段として名を連ねる。いまのところ、史上最強の女流といえそうだ。
ほかにも、女流の名は挙っている。天保十年に大橋柳雪が発行した『将棊見立相撲』には、八丁堀はる女、本郷まさ女、水野こう女、大島き代女の四人の名が見える。前二者は地名を冠しているところから、町人の妻か娘であろう。あとの二人は、下級武士の妻か娘ではなかったかと思う。
明治に入って、女流の系譜は完全に姿を消した。心得違いの連中が賭将棋を渡世とし、ために将棋の評判は地に墜ちた。男でも将棋に近づかなかったくらいだから、女性で将棋を指す者はいなかった。生活も苦しく、将棋を指す暇があるなら、生活を支えるために働かねばならぬ時代が、ずっと昭和の代までつづいていた。
ここ十数年来、女性の将棋熱は復活した。「思いどおりに作戦を樹てて、自由に駒を動かすことができる」とか、「創造の喜びがある」とか女性ファンは語っている。戦後は「強くなった」といわれる女性も、まだまだ盤上でしか「自由」を満喫することができないというのであろうか。
女性は終盤が弱い。また初心のうちは、持ち駒を惜しんで、好機を逸する例を多く見る。
それも、性というものであろうか。
26 親の死目に会えず-2009.12.01-
誤伝は恐ろしい。昔から、将棋を指す者は親の死目に会えないといわれてきた。私自身、貧しいなかで中学進学が許されたとき、小学校六年の担任の先生は、
「中学に行ったら、将棋はしないと約束できるかね?」
と念をおした。
いまも、その教師の強い語調が耳の底に残っている。そのころ、特に将棋に凝っていたわけではなかった。普通の子供と同じ程度に、緑台将棋を愉しんでいただけである。教師は、将棋は勉強のさまたげになると信じこんでいた。教師に限らず、その時代の大人たちは、たいてい、そう思いこんでいた。
昭和十年代の思い出である。中学から旧制の彦根高校に進んで寮生活に入ったときも、頑として駒を手にしなかった。あのころ、そうした間違った考えを注入されていなかったなら、ずっと将棋が強くなっていたろうにと悔いている。
いま、誤伝は、「昔から」と書いた。のちに、将棋史を研究するようになって、それが虚言であることを知って胸を撫でおろした。
江戸末期の戯作者、松亭金水は、『松亭漫筆』のなかで、「諺にも、囲碁将棋に溺るれば、親の臨終にも逢ずといふ」と書いた。そのころから、一部の頑迷な道学者のあいだで、そうした「諺」がささやかれていたらしい。
金水は、囲碁と将棋の両方に難癖をつけた。それが、いつの間にか囲碁のほうは免罪となり、将棋だけが汚名を着ることとなった。
「諺」の本来の意味は、毎年十一月十七日、江戸城の黒書院で催される御城将棋・御城碁に関することである。式日の数日前、将棋と碁の者は、それぞれ家元の家で内指といって、式日に将軍の前で披露する対戦譜を用意した。将軍の前で指し始めては、いつ勝負がつくか判らず、それで寛永十二年(一六七二)からは、内指(内調ともいう)する制度を採用した。
将棋と囲碁の者は、寺社奉行の支配に属する。俸禄を受け、現代風にいえば、国家公務員の身分だ。だから、内指の日は、たとえ親が危篤に陥っても帰宅はかなわない。対局の場に臨むのは、武士が戦場に在るのと同じことである。
その服務の厳しさをいったのが、「親の死目にも逢ず」ということであった。その誤伝が世間にひろまり、のちのちまでも語り継がれたのは、一つには、将棋や碁を職とする者にも責任があった。
明治初年は制度の変革期であり、幕府の禄を失った者は、日々の暮しにも困窮した。そこで、将棋や碁の者は賭に凝った。悪弊が改められず、世人は眉をひそめたという。
ただ、碁の者はスポンサーをみつけて、いち早く賭碁から足を洗った。将棋は、いつまでも賭将棋にとりつかれていて、将棋だけが悪役に仕立てられてしまった。
棋界入りを志した神田辰之助(贈九段)は、勘当されて家出をした。大正時代という、さほど遠くない日の出来事である。
いまは、高校では必須課目としてクラブ活動に取入れられるようになった。往時、進学に際して将棋を禁じられた私とすれば、うたた感慨にたえずといいたいところである。