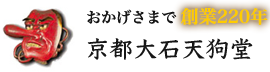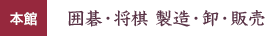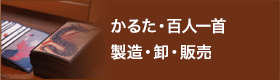将棋の豆知識61〜62 光風社 将棋101話 転用
61.虎班の駒 -2012.11.01-
根津宮永町の駒師、宮松幹太郎さんを訪ねたとき、二畳ばかりの工房には、仕上げを待つばかりの駒が置いてあった。一つは虎班、一つは赤柾ということである。その二つの工芸品を見て、いたく心を打たれたことを覚えている。
いままで見た駒とはたしかに違う。どうして、虎班とか赤柾といったたぐいものが、黄楊材のなかに混っているのだろうか。質問を発すると、駒師はちょっと首をかしげて、
「さあね。黄楊の奇形児じゃないですか」
深くは知らない口振りであった。
数日経って、荻窪に井伏鱒二先生を訪問したおり、その話をした。先生は、そういうことは三宅島の浅沼君に訊けば判るだろう、と神着村の浅沼悦太郎氏を紹介してくださった。
さっそく、浅沼悦太郎さんに手紙を書いた。すると、浅沼さんは、つぎのようなことを知らせてくれた。
御たずねの件
一、黄楊の虎班は根の部より生じたものと思います。根の部は櫛屋では用いませんので切捨てて居ります。櫛の名人、湯島天神上の三五郎さんの家に行けば、櫛にして居ります。
一、赤柾。これも櫛に不適当なるもので、素姓のよいマサ目のものの中で、アテ木といって水づいたところです。これは御蔵島の黄楊が良いことになって居りますが、どこのものでも使って居る間に、時々椿油でふくと赤いよい艶が出て参ります。(後略)
浅沼さんの解説に従えば、虎班も赤柾も黄楊の奇形児である。もっとも、あの逸品を奇形児と呼ぶのが失礼なら、稀少なるものとか、珍品といい直せばよろしかろう。
そうしたことがあって、宮松さんの工房にあった虎班と赤柾の駒は、いつしか私の所有に帰することとなった。
虎班は、柾目のなかに、虎の班点模様が美しく刷り込まれていることがごとくに見える。赤柾は、水にぬれたみたいに材質が赤みを帯びている。ともに、得もいわれぬ品格を漂わせる。
あるとき、将棋仲間の小沼舟氏がお見えになり、盤開きならむ駒開きをした。小沼さんも、その二つの駒が気に入ったらしかった。そこで、赤柾は手許に残して、虎班の駒を進上した。
いく日かすぎ、こんどは武蔵野市八幡町に小沼さんを訪ねて十番将棋を指した。終って、虎班の駒を駒箱に仕舞いながら、ふいに小沼さんは、こんな話をした。
—昨日、木山捷平さんが見えて、虎班の駒で対戦した。その日は不調らしく、木山さんは二連敗した。すると木山さんは、「駒のせいですよ。この駒は立派だが、目がちかちかして読みが乱れますね。馴れないせいでしょうかね」と敗戦を駒のせいにした・・・。
なるほど、虎班の駒は明るい電燈の下では、金属製品のように光り輝いて見える。目を悪くした木山氏には難物であったろう。といって、敗戦を駒のせいにするのは、どうであろう。
そういって虎班の駒を弁護すると、「いや—」とこんどは小沼さんは木山氏を弁護した。
「虎班は派手すぎて、木山さんの地味な作風と合わないんだよ。あんまり派手すぎるもんだから、木山さんは照れてしまって、日ごろの実力が出なかったのかも知れん」
先日、何年振りかで小沼さんを訪ねて、終日、将棋を指した。虎班の駒はよく手入れされていて、さながら新品のごとく美しい光沢を放っていた。
[後記]木山捷平氏は逝き、宮松幹太郎も若くして世を去った。
62.駒師追慕 -2012.12.01-
駒師の宮松幹太郎氏は、カンナ台の前で片膝立てて無心に駒を磨いていた。
仕事場は二畳敷きで、カンナ台、印刀、ウルシ碗、それに仕上げを待つ駒が幾組か置いてある。棚にも、未完成の駒がボール箱に入れて積み重ねてあった。
カンナ台の前に座る宮松氏の後姿は、なぜか老成した人のように見えた。ちょっと猫背に見えた。驚いたことに、こちらに向き直ったとき、しゃんと背筋をのばしている。それでも、話に熱が入ると立膝になり、すこし前かがみになる。そういう姿勢が一番楽で、立膝になると気持が落着くらしかった。
宮松氏は、関三郎八段の遺児である。父君から手ほどきを受けた後は、独力で、この道を開拓してきた。だから、カンナ台にしても、印刀にしても、駒の製作の道順も、他の駒師とは異る点も多くあるらしい。
いま、高級駒作りに従事する人は、十指を出ないという。もっとも、駒師の系譜は判然としない。戦前までは、豊島氏と奥野氏の二人が棋界を支えていた。その豊島氏は、駒師三代目と称する牛屋氏に師事したと伝えられる。とすれば、初代牛屋氏は江戸後期の人ということとなる。
現在の駒師は、いずれも戦前の豊島・奥野両氏の流れを汲む人である。豊島氏の直系の弟子に、木村文俊氏(十四世名人木村義雄の弟)がいる。奥野氏の弟子は、天童市の松田氏ということである。
その日、宮松氏を訪ねたのは、駒の製造法を教わり、駒の銘(文字)を見せて戴くためであった。銘は、苦心して集めて三十余を蔵しているときいた。「あなたは素人ですから」と宮松氏は、奥から駒の銘を持ってきて見せてくれた。
駒の銘は、駒師にとっては財産であり、だから、宮松氏は、
「公表されると、営業に差支えますので・・・」
写真撮影は遠慮してほしい、といった。
注文があれば、駒の銘を美濃紙に写して駒作りにかかる。そのために駒師は、手先が器用であるばかりでなく、書を能くしなければならない。宮松氏は、面相筆を用いる。それも、氏の発案であるらしい。
「一組の駒の銘を書くのに、どれくらいかかりますか?」
「一字に二分から三分。ですから、一組で四時間ですね。凝り出すと、反日かかります」
「一日に、いく組もできるのですか?」
「どんでもない。仕上げだけでも、一日かかることがあるんですから」
そんなことよりも、駒師の苦しみは別のところにあるらしい。機械の助けを借りて大量生産される天童駒が市場を制圧する。手作り専門の駒師には、その風潮が耐えられぬらしい。
「それに、駒作りは三十五歳が峠なんですよ」
と声を落としていった。
職人というのは、三十五歳をすぎると、急に腕が落ちる。視力が弱り、身体がいうことを利かなくなる。だから、職人は四十をすぎると、
「口で仕事をするようになるんですよ」
宮松氏は、駒作りを「天職」といった。いい駒を作ることしか念頭になく、会心の作ができれば、制作年月日を刻みこむ。会心作は、駒作りを始めてまだ二組しかないという。
「そいつを手放すときは辛くてね」
ぽっつり呟いた。そのとき、蒼白い顔に笑みがひろがるように見えた。